HSCって色々な感情に敏感で、ネガティブに考えたり凹むことが多いのは事実です。
子供が持つ可能性を少しでも伸ばしたいと一生懸命になるのが親心。習い事もさせてあげたい、頑張る力を育てたい、たくさんの経験をさせたい…と考えるものですよね。
しかし行き過ぎた心配や手の掛けすぎが、かえって子供を辛い状況に追い込むことになりかねません。
今回はHSCが習い事を始めるとき、また続ける中で、親はどのように応援・対応したら良いか、我が家の事例を踏まえてお話したいと思います。
 Milly
Milly娘は5歳から約10年間、ピアノ教室に通いました。習って良かった、今は親子でそう思うことができています。


やりたい!が初めどき
娘の場合、幼稚園でお友達がピアノを弾いていることに興味を持ったようで、自ら「習いたい!」と懇願し続けたことが習い始めるきっかけになりました。
「3歳」が良いって本当?
習い事によって3歳が良い、0歳から!1~2歳…小学生になってから等々、様々言われます。確かに、吸収しやすい年齢があるのは事実。脳の成長に関わる理由や、子供と先生との関係性を築きやすいという理由、学校の勉強との兼ね合いや送迎の問題などもあるでしょう。「3歳」を理想とする説もあながち間違いではないように思います。
しかし、習うのは子供自身。全ての子供、全ての親、全ての家庭に「3歳からがいい!」という説がぴったりマッチするかと言われると、正直そうだと言い切れない部分もありますよね。そんなことから、私自身は年齢にこだわる必要はないと考えます。
特にHSCの場合、先生や一緒に習うお友達との関係や、練習への取り組み方、継続できるかは慎重に考えたいところ。年齢にこだわらず、我が子が楽しく通えるかをじっくり見極める必要があると思います。
HSCは始めるときも慎重です
習い事を始めるきっかけは様々。体験学習に参加したり、友達と一緒に誘われることもきっかけのひとつ。どんなきっかけでも、そこには子供自身の「やってみたい!」という気持ちがあってこそ習う意味があるでしょう。
特にHSCは不安になりやすく、物事を慎重に考える傾向にあります。この先生と長い付き合いができるかな、教室の雰囲気に馴染めるかな…たくさんの不安を抱えてのスタートになる可能性が高いのです。
それを踏まえ、まずは体験。子供自身が教室や先生に安心感を抱き、「やりたい!」と言ったときは、習い始めるチャンスと考えて良いでしょう。
自分で決めることだから頑張れる
HSCは、幼くても色々なことを考えます。習いたい、そう言ったときは本当に考えた末の事と受け止めて大丈夫。自分自身で決めたことでこそ、子供は頑張れる力を発揮します。
では、親に無理強いされて始める習い事はどうでしょう。HSCはそこでもよく考えるでしょう。「習ったらママが喜んでくれるかな。」「嫌だって言ったら怒られるかな…」「あなたのためよってママが言うから本当にそうなのかもしれない…」
そのような形で始めた習い事で、子供が本当に楽しめるか、頑張れるかを考えたいものです。いつか「本当はやりたくなかったのに」「言われたから断れなかった」と言われ、結果良いものを生み出さない可能性も否定できません。
何よりも、子供の「やりたい!」という気持ちを大切にスタートさせるのがおすすめです。


親にできるのこと&すべきこと
さて、様々なきっかけで始めることとなった習い事。子供がHSCの場合、親と先生との関係性や応援の仕方等、送迎や欠席の対処など、配慮が必要な部分が度々出てきます。
先生との付き合い方
まずは先生との付き合い方。これはとても大切です。
HSCは、人の言動や目の動き等に非常に敏感です。先生が何気なくかけた言葉に傷ついたり、怖いと感じることが多いのです。まぁいっか!と流せないので、我慢が重なると辛くなります。楽しいはずの習い事、好きな習い事が嫌いになってしまう、本当は続けたいのに続けられない…
悲しいですよね。とても残念ですよね。
できるだけ先生との良好な関係を築き、好きなことを続けるために、我が子がHSCでありどんな特性があるのかは、先生に理解してもらうことが必要です。これは親にしかできないこと。理解のある先生なら、子供もきっと楽しく長く続けてくれるはず。頑張る力も育つはずです。
通う手段に配慮
HSCは習うこと、先生との関係だけでなく、通う手段、教室にたどり着くまでの道のりにも不安を抱きます。
1人で歩くことが不安、知らない人に合ったらどうしよう…、時間に間に合うかな…、帰りに雨が降ったらどうしよう…このように、様々な問題をイメージしては不安になってしまうことは少なくありません。
「自分の習い事なんだから、自分で行きなさい」と突き放すのではなく、子供の不安に寄り添ってあげることが必要。お迎えは時間より早く到着して教室前で待っていてあげたり、携帯を持たせていつでも連絡がとれるようにするなどの配慮は不可欠です。
欲を出さない
習い事を始めると、ついつい欲が出るのは親心。将来につなげる学びになればいいな、親がそう思っても、将来を決めるのは子供自身です。
ただ趣味で通いたいと考える子供もいるでしょう。それも続ける素敵な理由のひとつになることを理解したいものです。HSCはすぐに不安になります。自己肯定感を高めるために、習う→好き→自信が持てる!と発展すれば、それは将来までつながる大切なパワーになるはずです。
HSCは深く深く考えるのが特性のひとつ。大丈夫。親が思う以上に、将来のこともきちんと考える傾向にありますよ。
強制しない
HSCの場合、毎日の練習を強制したり、休まないことを強制するのはおすすめできません。特に、小学校高学年あたりからは、自分自身の考えに基づいて決めていかなければ子供自身が混乱します。「やらなければならない、でもできない、どうして自分はできないのか…」と悩みのドツボにハマり苦しくなります。
欠席が続いたとき、一番悩んでいるのは本人のはず。親は子供の心の状態を先生に伝えましょう。休むことが続くかもしれませんと伝えておけば良いのです。コンクールや大会、試験など、習い事の内容によっては結果に悪影響を及ぼすこともあるかもしれません。HSCの子供はその点もしっかり理解してのことだと考えましょう。ただし「結果が悪くても良し」と捉えているのではありません。気持ちと現実との境目で悩んでいるのです。まずは、そんな子供の心の葛藤を見守り、信じましょう。
少しでも手助けしたくなりますが、見守ることもまた手助けのひとつです。放置するのではなく、助けを求めたときにいつでも一緒に悩むことができる親でいたいですね。
HSCは少しのことを繊細に考え、感じ、敏感に受け止めます。子供をよく見て、声をかけるタイミングと言葉選びは慎重になってくださいね。


やめ時はズルズルになりがち
HSCは決断することが苦手。「よし!やめよう!」と本人が決断すれば簡単ですが、ズルズルと悩み、やめたいけどやめられない…といった状態になってしまう傾向にあります。



時間をかけて決めよう
欠席が続く=止める、きっぱりと気持ちを決められることができないのは、HSCの特性のひとつ。迷い、悩むのです。本人は「本当はまだ続けたい」「いつか再開したい」と考えている可能性があります。決められないうちは無理に決める必要はありません。教室から催促されれば別ですが、休会できるなら休会し、ゆっくり考えさせてあげたいですね。
親の判断でやめることを急いでしまうと、子供は通えなかった自分自身を責め、意欲を失い、自己肯定感が下がってしまいます。
途中で止めることは悪いことではありません。ゆっくり考えた末の結果をしっかり受け止めて、子供の考えを認めてあげることも親にできる大切な応援です。
自分で結論を出すことが大事
娘はピアノを長期間習ってきましたが、学校に行けなくなると同時にピアノも休みがちになりました。先生に事情を伝えたところ、「本人の気持ちがいちばん大切。いくら休んでも構いませんよ。やりたいと思ったときにいつでも来てください」と理解してくださったことが何より心強かったです。そのため、学校に行けるようになるとピアノもまた始めようと前向きになり、スムーズに再開することができました。
最終的には再び学校へ行けなくなり、本人が「今は学校のことで頭がいっぱい。ピアノのことを考える余裕がないからやめたい」と決めました。
HSCにとって、決断には勇気も気力もいること。何日も何週間も何カ月もかかるかもしれません。でも、決めた結果がどうではなく、決断に自分の力を使ったことに大きな意味があったように感じています。
親としてはつい早く決めてほしい、とイライラしてしまうもの。そこでぐっとこらえ、子供を信じて見守ってあげてください。習い事を理由に、親子関係がぎくしゃくすることだけは避けたいものです。
まとめ
子供が何かに夢中になり、ぐんぐん上達する姿は親にとって大きな喜びです。もっと上達してほしい、高みを目指してほしい、期待も膨らみます。
でも、習い事は子供が自分自身のためにすること。特にHSCの場合はプレッシャーに弱く何事も簡単に受け流すことができないので、悩み苦しむ場面が多いかもしれません。だからこそ、親の方が一生懸命になりすぎず、黒子のような存在でゆったりと見守り応援してあげたいものです。
Have a happy time!


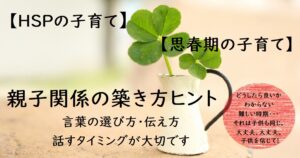






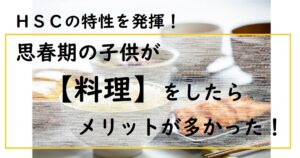
コメント